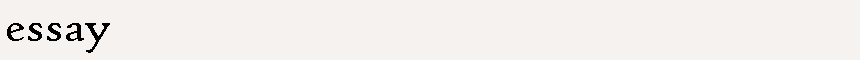神戸のこと 2020.01.17
神戸の震災から25年。もうあれから四半世紀もの月日が流れた。
生まれて初めての大きな震災を目の当たりにして、でも、こんな大きな震災を経験することはもうきっと生涯ないだろうと思っていたので、あれから日本各地で大きな震災が次々と起こることになるなんて、あの頃は想像もしなかった。
だから、震災を忘れない日は、一年に何日もあるわけだけれど、神戸の震災がわたしにとって最も忘れられない日になっている。
当時わたしは、大阪の東淀川区というところに暮らしていた。大好きな阪急電車沿線。
阪急電車で30分ほどで京都へも神戸へも難波へも出れて、梅田までは10分という便利で暮らしやすいところだった。
お笑いが大好きだったわたしが、10代の頃に一番憧れていた街が大阪で、大阪にいられるだけでうれしくて、阪急電車に揺られては、休日はいろいろなところへ出かけた。
中でも一番好きだった街が神戸だった。
なぜなら、そこには憧れの人がいたから。
神戸の小さなお店で髪を切ってくれていた美容師さん。今思えば、まだ20代前半のお若い年齢だったと思う。当時のわたしにとって年上の人というのはものすごく”大人”に見えて、恋愛感情ともちょっと違う、まさに憧れのような気持ちだった。
美容師という職業の人に抱いていたイメージは、見るからにオシャレでちょっと近寄りがたいイメージだったけれど、その人はぱっと見、美容師らしからぬ地味な風貌で、でもよくよく見るとさらりと素敵なシャツを着ていたりして、オシャレ全開!でないところもとても好きだった。物腰も静かで穏やかな人。
一緒の美容院に通っていた友達もその人のファンということがわかって、よく美容師さんの話で盛り上がった(何かを追いかけているときってどうしてあんなに楽しいのだろう!)。
そんなとき、神戸の震災が起こった。
神戸と聞いてすぐ浮かんだのは、その美容師さんの顔。あの頃の主な連絡手段は、固定電話のみ。その電話さえも回線はしばらく繋がらないままだった。
わたしは幸い被害はなく無事だったのだけれど、すぐ近くに住んでいた友達は窓ガラスが割れたり物が壊れたりと被害も大きかったようで、建物の構造上のことを初めて意識した出来事でもあった。
その後の余震が恐ろしかった。夜寝るときもいつでもすぐに外へ出られるように、パジャマでない服を着て、靴と貴重品を詰めたリュックを枕元に置いて寝る日々。絶えず余震があるので、揺れていなくてもずっと揺れているような錯覚に襲われて、熟睡できるはずもなく心休まるときがない。震災から数日が経ったそんな頃、留守番電話に美容師さんからメッセージが入っていた。
無事ですか?今、美容師仲間たちと近くの小学校を借りて営業を再開しています。
と。
同じくその電話を受けたファン友達と、神戸に行こう!となって、神戸に向かうことにした。
電車は神戸までは復旧しておらず、途中の西宮で降りて、臨時のバスに乗って数時間かけて神戸へ向かった。神戸が近づいてくると、これが現実とは信じられないような景色が広がっていた。
ガレキの山山山。ビルもほとんどのビルが傾いているので、どれがまっすぐに建っているビルなのかわからないほど。これがあの大好きだった神戸の街だろうかと目を疑うような悲惨な光景だった。
無事に美容師さんの元気な姿を見届けて、髪を切ってもらって、その後ボランティアに向かった。
学校で避難生活を送る子どもたちと一緒に遊ぶというボランティア。
教室も体育館もすべてが避難所になってしまい授業が受けられなくなった子どもたちと一緒に、身体を使ってゲームやスポーツをする。
みんなすごく元気でこっちが元気をもらうほど明るかった子どもたちだけれど、もう帰る時間だ、となった時に様子が一変した。
帰るなーーー!!!ありったけの力で叩いて、足を踏んづけてくる。
子どもたちに羽交い絞めにされながら、叩かれる痛みと子どもたちの痛みが同時に伝わってきて、痛いーやめてー!と言いながらほとんどもう泣きそうだったけれど、外から来た者が簡単に泣いてはいけないと思っていたし、また来るから!と言って逃げるようにその場を後にした。
子どもたちはみんなわかっている。本当は一番甘えたい両親には甘えられないこと。自分だけでなくみんなが大変なこと。外から来たわたしたちには甘えてもいいこと。
でも外から来た人はみんなすぐに安住の地へ帰ってしまうこと。
ぼこぼこに叩かれた痛みは、子どもたちの行き場のない痛み。
バス乗り場まで歩いていると、ガレキの山の中から、けたたましく目覚まし時計が鳴り続けている。
あの日から誰にも止めることができない目覚まし時計が、もう一週間近くもガレキの下で毎日朝と夕方の同じ時間に鳴り続けているんだと思ったら胸がぎゅーっと苦しくなった。
帰りのバスでは友達もわたしもずっと無言だった。
ただ美容師さんに会いたいという思いだけで何時間もかけて行った神戸。神戸へ行くならボランティアしよう!なんて簡単に思っていた自分。
そんな未熟な自分に子どもたちの気持ちも震災の大きさも受け止められるはずもなく、ただひたすら無力感があるだけだった。
あの光景を一緒に見た友達は、4年前に他界してしまった。
美容師さんは、何年か前にふと雑誌で見かけてびっくりしたことがあったけれど、あれ以来会っていない。
あの頃小学生だった子どもたちも、もう親になったりしているんだろうなぁ。
何年か後に訪れた神戸は、ぐんぐんと力強く復興して、震災の跡形もない美しい街だった。
神戸のことを思い出すたびに、どこか後ろめたいような気持ちになっていた。
でもあの頃、頭で考えるよりも先に行きたい!と思ってすぐに神戸に行った自分を、今はちょっとうらやましく思う。
本のこと 2019.02.01
ときどきふと手に取って読み返す本がある。
「たましいの場所」早川義夫さんのエッセイ集。
最初に読んだのはもう6年くらい前だと思う。
職業柄図書館で本を手に取ることが圧倒的に多かったので、この本との出会いも図書館だった。
とある本の中で、宮藤官九郎さんが、たまたま喫茶店で手にしたというこの本のことを大絶賛されていたので、わたしも読みたくなってしまった。
早川義夫さんの肩書を見ると、元歌手、元書店員、再び歌手とある。
最初にこの本を読んだときは、早川さんが歌手だとは知らなかった。
10代の頃にジャックスというバンドで歌手デビューし、その後23歳で早くおじいさんになりたいと思って音楽を辞めて本屋さんになり、その後二十数年経って再び歌い始めたという、その経歴だけでもうとても気になってしまう人だ。
図書館で読んで好きになった本は買うことに決めていて、今はこの本は手元にあり、その後に出た早川さんのエッセイ集も2冊買った。
この本を手に取るときは、たぶんちょっと心が弱っているときだと思う。決まってそんなときに読むものだから、毎回どこかで泣いてしまう。
自分の心の中にある何かとその人の心の中にある何かがぐっと近づいて触れ合うとき。
それは、目の前にいる人だけではなくて、本の中のその人や、映画の中のその人や、歌の中のその人。
心が動くということはすごいことだと思う。
普段はなんでもないことのように受け流したり、笑い飛ばしたり、そんなことも必要なことだと、年を重ねてずいぶんと思えるようにはなってきた。
日常で歌うことが何よりステキで、日常の中で歌が歌えていたら歌を歌う必要はない、というこのエッセイの中にある言葉にはとても共感してしまう。
まだ歌を歌わずに生きていけそうもないわたしは、日常で歌えない歌がたくさんあるのだろうか。
お世話になっている四日市のライブハウスガリバーのママが早川さんの大ファンで、以前にガリバーでライブをされた時のことなど、早川さんの話をいろいろ聞かせてくれる。
まだライブは拝見したことがなかったので機会を狙っていたら、昨年突然の活動休止。
ああ、あの時行っておけばと悔やんでも、次はないのだった。
けれど同時に思う。
ずっと歌い続けていたら、まだ知らない誰かにいつか会えるかも知れない。
エッセイを読み終えてそんなことを思いながら、
早川さんの「この世で一番キレイなもの」を聴いている。
ミュージカルとわたし 2017.04.01
映画「ラ・ラ・ランド」を観た。
久しぶりのミュージカル映画に興奮。
アメリカ映画を映画館に観に行くことがもう数年ぶりで(一時期は好きな映画がたくさんあった)、
すでに観たという周りの人たちにはあまり好評ではないし、と少しの躊躇があったもののミュージカル映画と聞けば身体が動いていた。
何を隠そうミュージカルが大好きなのだ。
サントラを買い毎日聴いていたら、映画のシーンが次々と思い出されていてもたってもいられなくなり、2回目を観に行ってしまった。
大好きな映画がまたひとつ増えた。
一人弾き語りで唄い始める前に、少しの期間、地元の ミュージカル劇団でお世話になっていたことがある。
ミュージカルを人生で初めて観たのは30代。
10代20代の頃からライブハウスに足蹴く通っていたわたしにとっては、ミュージカルというのはなんとも不自然なもののようで気が進まなかった。
観ず嫌いだったわたしのミュージカルのきっかけは、好きな俳優さんが出ていたので生で見てみたいというなんともミーハーな気持ちからだったのだけれど、観に行ったらその俳優さんのことなど忘れて(笑)、何よりミュージカルそのものの素晴らしさにすっかり魅了されてしまった。
最初の一幕の間は、セリフが歌になっているところがやはりどうしても違和感があったのだけれど、休憩をはさんで二幕が始まると、その世界の中にどっぷりと入りこみ、いつしか違和感は高揚感に変わっていた。
日々の中でも唄いたいくらい嬉しいことや、踊りたいくらい 楽しいことや、叫びたいくらい悔しいことなんかがあって、でも実際に唄ったり踊ったりなんてしないけれど、その表現されずに心の底に埋もれてしまった数々の 思いは、一体どこへ行ってしまうのだろうと思うことがときどきある。
ミュージカルを観ていると、その埋もれてしまった思いのようなものが解放されていくような感覚を味わえるのかも知れない、そんな風に感じたのを覚えている。
初ミュージカルを観終えた後は、友達とお茶もせずにそそくさと家に帰り、しばらく茫然としてしまった。
まさかわたしがミュージカルにはまるなんて!
これは気の迷いかも知れないと思ってしまったのは、新しいものをすぐには受け入れられないほど歳を重ねていたからかも知れない。
この気持ちをはっきりさせるべく、もう一度同じ舞台を観に行くことにした。
もう一幕から違和感は全くなくひとつずつの場面をじっくりと味わうことが出来て、気の迷いではなく、わたしはミュージカルが好き!ということを確信した。
それからは、たくさんのミュージカルを観に行った。何しろそれまでに全く観たことがないものだから、どれもこれも新鮮で刺激的。ミュージカル映画もその頃はたくさん観た。
ミュージカルに出会ってもうひとつ大きく変わったことがある。
それまでは、誰かのライブに行っても自分は見る側で、それが本当にとても楽しかったので、ステージの側に 行きたいと思ったことはなかったけれど、舞台の上で、唄い、踊り、革命を叫ぶ人たちを見ていたら、あっち側へ行ってみたい!と思う自分がいることに気づいた。
歌も芝居もましてやダンスなんて、全くやったことのないもう若くもないわたしが、その後、劇団の扉を叩くことになる。
そんなわたしを、劇団のみなさんはあたたかく受け入れてくれた。
今思うと恐ろしいことをしたものだなと我ながら思う。
わたしはきっと何のお役にも立てなかったと思う。
でも、演劇という未知なる場所でわたしが得たものはたくさんあった。
本番前の連日の稽古は夜中まで続くこともあり、稽古は正直楽しいとは思えないこともあったけれど、本番をみんなで乗り越えたときの喜びは、それまでの人生で味わったことのない達成感だった。
それを自分の身体を通じて経験できたことは、わたしにとってはとても大きなことで、その時間が今の道につながっているのだと思う。
そんなこんなで、久しぶりにミュージカル熱が復活。
ラ・ラ・ランド一色の毎日。
全曲どれも好きだけれど、
ミアがオーディションのシーンで唄う歌がとても好き。
夢追い人たちに、乾杯
愚かに見えるかも知れないけれど
胸の痛みに、乾杯
わたしたちの引き起こすゴタゴタに、乾杯 ・・・
だからおいで、反逆者たちよ
波紋を生む小石よ
画家に、詩人に、役者たちよ
夢追い人たちに、乾杯
愚かに見えるかも知れないけれど
張り裂けそうな心に、乾杯
わたしたちの引き起こすゴタゴタに、乾杯 ・・・
(ラ・ラ・ランド サウンドトラック「AUDITION(THE FOOLS WHO DREAM)より抜粋」)
まんぼー 2016.05.11
「菊乃井」にて旧友たちと再会。
京都老舗料亭・露庵「菊乃井」の料理長をつとめるのは、
10代の頃からの旧友まんぼー。
料理場を仕切るいい年の大人の男性に、まんぼーもないけれど、
まんぼー以外の呼び方を知らないのだから仕方ない。
若い修業中の板前さんたちが行き来する中、”まんぼ~まんぼ~”
と連呼するのもどうかと思ったけれど、カウンター越しに
”まんぼ~”が何度もこだました昼下がりの菊乃井。
料理が大好きで、いやいや、彼にとっては、
生きることそのものがもう本当に大好きで、
心のおもむくままに毎日を自分自身を
全力で楽しんでいたようにしか見えなかったあの頃のまんぼー。
大学を卒業してから専門学校を出て、料理人を目指して修業の道に入った。
その世界では、遅すぎるスタートとも言える
スタートだったようだけれど、そんなことは
まんぼーには全然関係ないように見えた。
それでも、大変な修業時代をわたしは少しだけ知っている。
わたしなんかには、到底耐えられることの出来ない厳しい世界。
そんな彼が、料理長になったと風のうわさで聞いたのは5年ほど前。
その頃、いつか自力で夜の「菊乃井」の暖簾を
くぐれる自分になると密かに誓っていた。
けれど、5年経った今、わたしはあの頃よりも貧乏になり、
毎日の生活を回していくだけでいっぱいいっぱいのまだまだの日々。
みんなもそれぞれの生活に忙しく、揃って会える余裕もなくただただ
時が過ぎていた。
そんな中、今年の年明けに大切なわたしたちの友達の一人が
病気で他界した。
いつか・・・いつか・・・と言っていたら、
会いたい人にもう二度と会えないままお別れになってしまうかも知れない。
人は、必ず死んでしまうのだから。
今こうしていることがあたりまえではないというあたりまえのことを、
胸に刻んだ出来事だった。
いつか・・・なんて言ってないで、今会いたい!
ちょうどニュージーランドから友達が帰省したタイミングで、
また3人での再会を切望した。
そして、ほとんど二十年ぶりくらいの再会が実現した。
夜の菊乃井へ自力で・・・というのは叶わず、
”情けないけれど、今の自分ではまだまだです。”
と、まんぼーにメールを入れると、
”まだまだとか情けないとかいらんしね~
マッキーが何をしていようとも何をしていないとしても、
マッキーは僕らに愛されてしまってるのだから(ニカ)~”
というメールが届いた。
ほとんど二十年近くも会っていないというのに、
このメールから漂ってくる空気が、あの頃の
まんぼーとあまりに同じで、びっくりする。
あの頃は、まだ携帯もメールもない時代。
わたしが落ち込んでいるタイミングを見計らったかのように
ときどきまんぼーから手紙が届いた。
その手紙があまりに可笑しくて、
あまりに温かいものだから、
引っ越しをするたびにその思い出と対面して、
捨てられずに今でも大切に取ってある。
ランチタイムにお邪魔して、仕事の合間を見て
カウンター越しにいろいろと話した。
話しながら気づいたけれど、昔のことは楽しいことしか
覚えていないものなのだということ。
亡くなった友達のダンナさんが、
4人で遊んだりしていた頃が本当に楽しかった!と、
よく話していたと教えてくれた。
旅立った彼女もこんな風に楽しそうに思い出を話していたのかも知れない。
あの頃は、ちょっと奇天烈だったまんぼーは、
二十年経ってまっとうで立派な料理長になっていたけれど、
やっぱりまんぼーはまんぼーだった。
もうわたしたちは、酔っぱらってベランダからわけのわからないことを叫んだり、意味があるのかないのかわからない問いを繰り返し延々
夜通し長電話をしたり、遊園地で水をかぶってずぶぬれになって
大笑いするようなことはない。
ちゃんと分別のあるそこそこまともな大人になった。
それでも、決して消えてなくなることはないもの。
それは言葉では表せないけれど、そういうあの頃と何も
変わらない何かが確かにそこに存在していたように思う。
心斎橋にあったガネーシュというおいしいチャイが飲めるお店。
みんなあのお店が大好きで、よくそのお店に通った。
その頃インドの旅から帰ってきたまんぼーから、チャイを飲みながら
インドのことをたくさん聞いたお店。
今はもうそのお店もなくなってしまった。
いろいろなことは少しずつ形を変えていく。
いつまでも同じところにはとどまれない。
変わったものと変わらないものを両方持って、
わたしたちの再会の時間が終わった。
思い出話もすごく楽しかったけれど、みんながみんな
今の人生をとても気に入っているように見えてうれしかった。
そして、何よりまたこうして元気に笑顔で会えたことが
何よりただただうれしくてうれしくてたまらない。
限りある人生、今を精一杯!
出会ってくれてありがとう。
エディット・ピアフ 2016.02.11
影響を受けたアーティストは?と聞かれると、
エディット・ピアフの名前をあげているのだけれど、
ピアフの歌を特別に好んで良く聴いていたわけではない。
2007年に公開された映画『エディット・ピアフ~愛の讃歌~』。
もしかしたらこの映画をこの時のタイミングで観に行かな
かったら、一人で歌を唄い始めることはなかったかも、
というほど、この映画を見終えた後に、わたしの中で
何かが大きく変わったのだった。
ちょうどこの頃のわたしは、白紙だった。
これからは、自分が本当にやりたいことをやろう。
30代に突入していた遅すぎる決意の先で、
やりたいと思ったことを年齢とか環境を言い訳にせずに、
とにかくやってみよう!と、いくつかのことに手を出して、
それらが一段落すると、結局わたしは何がしたかったのか、
何がやりたいのか、ますますわからなくなってしまった。
精神的なものからなのか何なのか、なにやら体調も悪く、
ほとんど部屋に引きこもっていた。
そんな中、エディット・ピアフの映画のことを知った。
直感で、これはどうしても観たい!と思った。
幸い当時住んでいたところは、映画館まで車で5分も
かからないような距離。
それでも映画が始まる寸前まで体調は悪く、冷や汗が
止まらない。
やっぱり帰ろう、でも観たい、でも、、やっぱり無理かも、
何度も何度も気持ちが揺れたけれど、映画が始まったら、
そんなことも忘れて、映画の世界にのめりこんでいた。
壮絶なピアフの人生を見た。
たった2時間だったけれど、ピアフはあまりにもピアフを
生きていた。
歌うことはピアフの全て。
不幸になるために生まれて来たのじゃないかというほど、
次から次へと容赦なく過酷な人生が展開していく。
歌うことがピアフを支え、壮絶な人生を生きれば生きるほど、
歌はすばらしいものへと昇華していく。
はじめは、路上でアカペラで一人で歌を唄い始めたピアフ。
その姿を見たときに、やっぱり”歌を唄いたい”という思いが
自分の中にどうしようもなくあることに気づいてしまった。
”やっぱり”というのは、唄いたいけれど楽器が出来ないから
一人では唄えない・・・と、また言い訳を用意して途方に暮れていた
自分がいたのだ。
一人きりで、何も持たずに路上で唄うピアフの姿に打ちのめされた。
いつだってどこだって、今すぐにでも、歌は唄える。
それをやるかやらないか、ただそれだけのこと。
そうは言っても、いきなり路上でアカペラで唄う勇気がないわたしは、
相棒となるギターを手にすることにした。
ピアノは、小さい頃何年も習っていたのに悲しいくらい上達せず、
人生の至極早い段階で、わたしには音楽の才能はないのだと
嫌というほど思い知らされてしまった。
それを肝に銘じていたので、憧れはありながらも、自分が
音楽に携わることにはいつもどこかで、無理、できるわけない、
とブレーキをかけてしまっていた。
それでも音楽は大好きだったから、いっときもわたしの側を離れる
ことはなく、歌を聴くことや誰かのライブを観に行くこと、いつも一番
楽しいことの中心には、音楽があった。
ギターを自らの意志で手にしたときに、ずっと片思いで追いかけ
続けてきた音楽に、初めて一歩近づけた気がした。
昨年は、ピアフの生誕100周年。
大竹しのぶさんの舞台『ピアフ』の再演が決まった。
まだ舞台は観たことがなく、とっても観たいけれど、おそらく
今回も観に行けないので、こうしてまたピアフとの出会いを
振り返っている。
”あたしが歌うときは、
あたしを出すんだ。
全部まるごと。”
-舞台『ピアフ』より-
山のこと。 2015.10.09
山を登るようになって、12年。
運動が苦手なわたしが、山なんて登るようになったのはどうしてだっただろうと思い返してみると、最初のきっかけは、ネガティブな出来事からだった。
突然右手が痺れて治らなくなった。
今思うと腱鞘炎のようなものだったと思うのだけれど、
原因不明の痺れに毎日憂欝な気分が続いていた。
病院へ行っても原因はわからず、結局半年くらいずっとびりびりと
右手は痺れたままだった。
ひととおり手を尽くした頃に、マイナスイオンを浴びたい!
という思いに取り憑かれた。
なぜマイナスイオンだったのかはわからないけれど、身体が
自然を求めていたのだと思う。
マイナスイオン=山と思い込んでいたので、山しかないと思った。
その頃の職場には登山を趣味とする人が何人かいたので、
気づいたら、わたしを山へ連れて行ってください!
とお願いしていた。
職場のみんなで行った最初の登山は、さんざんだった。
まず。登山というものを全然わかってなかった。
遠足気分で、ステンレスの二段の重いお弁当箱に魔法瓶の水筒、
山は寒いという思い込みから何枚も綿の服を重ね着。
登り始めてあっという間に、慣れないザックの重さと重ね着によって
熱が発散されずに、動けなくなってしまった。
なんとも、上司にお弁当箱を持たせてしまうという失態。
みんなに助けてもらってなんとか登頂。
初めての登山の感想は、ただただ、しんどかった。
それなのに、下山したらまた山へ行きたいと思う自分がいる。
最初の登山から数日後、また同じ山へ登ってみることにした。
今度は、なるべく荷物を軽くして。
二回目は、自力で無事登頂。
やっぱりしんどいことに変わりはなかったけれど、初めて感じる
筋肉痛さえも喜びに変わるほどの充実感だった。
生きてるってことを身体で実感するってこういうことなのかと
思うほど。
それから、ときどき山を登るようになった。
三重県には、1000メートルくらいのちょうど日帰り登山できる山が
たくさんある。
ひとつずつ新しい山を知っていく喜び。
季節が違うと同じ山でも全然違う景色を見せてくれる。
山で食べるものすべてが嘘みたいに美味しい。
風に揺れる葉っぱの音。手が届きそうな大きな空。湿った土の匂い。
ときどき聴こえてくる鳥たちのかわいい鳴き声。
いつか、違和感を感じたあのこと、あの人に言われた一言、
あれって嫌味だったのかな、ああ・・また上手く出来なかったな、
どうして私はダメなんだろう、、
そんな風に下を向いて落ち込んでたこと、
そんなこと全部が全部どうでもいいことに思える。
よく人から”考えすぎ”と言われる。
自分でも自覚はある。
けれど、考えてはいけない・・・ということをまた頭で考えてしまう。
これはもう性分ではないのか。
後天的にというよりは、生まれながらにして持っている性格。
そうは思っても、やっぱり考えすぎてぐるぐるになってしまうことは、
時にとてもしんどい。
大きな頭を抱えて、細い足でひょろひょろと生きている下界のわたし。
山の中では、さくさくと落ち葉を踏んで歩いている自分の足音だけが
響いている。
一歩一歩ひたすら足を前へと動かしていく。
何かより上でもなく下でもなく、意味もなくただ存在する自然の一部。
わー自分ってちっぽけだなぁと思う。
そう感じられるとき、ものすごく気持ちが楽になる。
ぐるぐるになったものが、ひとつずつほどけて空にとけてゆく。
さらさらと心地よい風が身体を吹き抜けていく。
そんな気分をわたしは、山で初めて味わったのだった。
あせる気持ちが出てきたときにいつも思い出す。
山を一歩一歩歩いている自分を。
どれほど装備を完璧にしても、どれほどトレーニングを積んでも、
一歩一歩自分の足で登っていかない限り、頂上には辿り着かない。
そして、自分の力だけでもまた、辿り着けない。
自然も味方にして、やっと見れる景色があるということ。
わたしは、山からいつもたくさんのものをもらっている。
山は、何かを教えようとか気づかせようとか、人を癒そうとか
好かれようとか、すごいだろって見せつけようとか、
そんなのは何にもなく、ただいつもそこにあるだけなのだけれど。
山を知れて本当によかった。
山は、大きい。
そんな山に少しでも近づきたくて、山を登るのかも知れない。
それにしても人生は、
一見ネガティブな出来事が、その後、見たこともない景色に
出会うためのすばらしいことへ続いていることがたくさんあるから
わからない。
本当には、何も心配することなんてないんだなと思う。
つづく。
同級生という贈り物 2015.07.23
地元に居ながらにして、学生時代の同級生や幼なじみと会うということがほとんどなかったのだけれど、ここ最近、同級生たちと再会する機会がパタパタと訪れた。
20年以上もの時を経ての再会となった同級生もいて、最初はちょっと照れ臭かったけれど、少し話したらすぐに会っていなかった長い年月は吹き飛んだ。
学生時代の思い出話もしたけれど、そんなのはほんの少しで、ほとんどが今現在の話やこれからのことだったのがとても新鮮だった。
もう今は、同じものなんてひとつもないのに、ただ一点同級生であるということだけが、こんなにも無条件の安心感につながっているなんて。
歳を重ねた証拠かも知れないけれど、ぐるぐるっと人生を一巡二巡して再会出来た喜びは、自分が想像していた以上のものだった。
まだ何者でもなかった十代の頃、何も持っていなかったし失敗さえも知らなかった頃。
あれから、それぞれが手にしたもの、手放したもの、積み上げてきたもの、なくしたもの、そういうものが背景みたいに浮かんできて、ときどきなんとも言えない気持ちになったりもした。
同じ時代を生きてきたみんながそれぞれの場所でそれぞれにがんばっている姿に会えたことは、これからもわたしの見えない大きな力になっていくと思う。
学生の頃からそうで今も変わってないねーと指摘されたことがあった。
十代の頃は、人からそれを言われる度に傷ついていたような気がするけれど、今やそれがわたし!と開き直る自分がいて自分でも驚いた。
わたしはこれからもたくさんの山を登って、たくさんの景色を見てみたい。
だから、きっとこれからも懲りずに何かを変えようともがいていくのだと思う。
いろいろが移り変わっていく中で、それでも変わらずに「変わらないもの」があるとしたら、それはもう大いに祝福すべきものだから、誰に何を言われようとも、開き直りとも違って、ちゃんと自分で自分を○にしてあげたい。
道なき道の途中で、ひととき交わった時間は、とても素敵な時間だった。
じゃ!と手を振って、またそれぞれの道。
わたしはわたしの山を今日もコツコツ一歩一歩。
孤島にて 2015.06.22
歌を聴いてくれた方やCDを買ってくれた方、わたしのことを全然知らずにブログで知ってくれた方、いろいろな方からときどきブログを通じてメールが届く。
いつかは、北海道の看護師の方からメールをいただいた。いつも病院で患者さんと一緒にCDを聴いてくれているそうで、その様子やブログの感想なんかがときどき届いた。
会ったこともない方だけれど、不思議と通じ合えるものを感じていて、メールはいつも励みになっていた。
歌がその人とわたしを繋げてくれたんだと思うと、こんな素敵なことってあるだろうかと本当に嬉しくなったのを覚えている。北海道を離れて、しばらくカンボジアへ行くとのことだったけれど、今も変わらずお元気にされていることを願っている。
先日、小説家の栗林佐知さんからメールをいただいた。
栗林さんの著書『はるかにてらせ』の感想をブログに書かせていただいたのがきっかけで、ご本人からメールが届いた。『はるかにてらせ』は、いくつかの作品が入った短編集で、読み進めるうちにどの作品にも何か共通する部分があり、そこに強く心を揺さぶられた。
ご本人のあとがきによると、
“主人公たちは概ね、おそらく人生初期に力を奪われたため、みんなが軽々と飛び越える水たまりであっぷあっぷする人たちです。「ダメ人間」「イタい人」と言われそうですが、今や否定ばかりされて混乱し、人が怖くなるのは特別な人だけではないでしょう。ダメでもイタくても「どっこい生きてる」主人公たちが我ながら立派に見えてきました。“
とある。
わたしは、どこか“生きにくさ”を持った主人公たちに自分を重ねながら読んでいた。やがて、自分の人生を本当の意味で大切に生きていくために反逆に出る彼女たちの姿にわくわくしながら。
まさかご本人の目に止まるとは思わず、思いのまま書かせていただいた感想だったけれど、ブログを見てくださった後にわたしのCDも聴いていただいているとのことで、その感想もとても嬉しく、本当に素敵な出会いをいただいた。
SNS時代の到来で、たくさんの人といつも繋がれるようになった。
わたしはSNSの世界はまだ知らないのだけれど、もしもツイッターやフェイスブックなどをやっていたら、と時々想像することがある。でももしかしたらその中では、ブログに書いているようにはのびのびと本の感想を綴ることはなかったんじゃないかと思う。
見たいときに見たい人だけが自由に見れるブログは、わたしにとってはとても気持ちが楽で、のびのびと発信できる。続けることが出来たのは、マイペースなわたしには向いているツールだったからだと思う。
とはいえ、ほとんどもう陸の孤島状態ではあるのだけれど、こんな風に予期せずときどきやって来てくれる船を見つけたときの喜びは、孤島ならではの醍醐味なのかも知れない。
簡単に繋がれる時代だからこそ、繋がるために知らずにかけた時間や遠回りが、繋がれたときの特別さと喜びをより大きくもたらしてくれる気がする。
以前旅をしたときに、島へ移住して暮らしている人が、なんでもそろっている都会で暮らしていたときよりも何もない島に来てからの方が、なぜか本当に繋がりたい人と繋がりやすくなったと言っていたのがとても印象的だった。
わたしも、心地よくのびのびとした、けれどときに孤独な、ほとんど手つかずの自然が残るまだ何もないこの小さな島で、ぴゅ~っと風に吹かれながら、いつかやってきてくれた船に思いを馳せたり、まだ見たこともない船たちを楽しみに待ちながら、“わたしはここにいます”と、ときどき旗をなびかせていけたらいいなと思う。
道しるべ 2015.04.01
人前で歌を唄わせていただくようになってから6年が経った。
ギターを手にして唄い始めたのは、ほとんどその一年前だから
もう7年近くになる。
唄いはじめたと言っても、万事整って晴れて初ステージというわけではなく、
すべてが見切り発車甚だしいスタートだった。
ギターもまだまだ全然弾けてなかったし、オリジナル曲もなかった。
それでもあの時は、今唄わなければもうこの先生きていけないんじゃないか
というほどの切実さでギターを手にしていた。
足らないものだらけの中に、あふれるほどにあったのは「うたいたい」
という思いだけ。
そんなわたしが初めて歌を唄ってお金をいただいたのは、唄いはじめる
前からよく通ってた大好きなお店の友達が企画してくれたライブだった。
大きなテーブルがひとつだけの、身体にやさしいおいしいごはんの
食べられる小さなお店。
友達と時間を忘れて何時間も話したり(オープンから閉店までいたことも!)、
一人でゆっくりと本を読みに行ったり。
時間ができるといつもその場所へ足が向いていた。
おいしいごはんはもちろんだけれど、ほどよい距離でいつも自然体で
そこにいてくれる店主のMさんに会いに行くのも楽しみのひとつだった。
そのお店の屋根裏の空間が雑貨屋になって、その雑貨屋のYちゃん
とも仲良くなった。
店主のMさんが海外へお嫁に行くことになって、Yちゃんが下の
お店も一人で切り盛りするようになった。
あのひとつきりの大きなテーブルで、編み物を教えてもらったり、
悩みを聞いてもらったり、お互いの今までのことやこれからの夢や、
たくさんの話をした。
唄いはじめたことを知っていたYちゃんは、屋根裏でライブをやろう!と
企画してくれた。
今思えば恐ろしいようなことだけれど、そのライブが決まったときですら、
まだオリジナル曲は一曲もなかった。
だから嬉しかった反面、曲ができなかったらどうしよう…
お客さん来てくれなかったどうしよう…
今のわたしがお金をいただいて歌を唄ってもいいのかな…
いくつもの「でも」に支配されて弱気になったわたしに、それでもやろう!と
Yちゃんが背中を押してくれた。
わたしを信じてくれたYちゃんの気持ちは、今でもわたしの大きな
財産のひとつ。
もしかしたら、わたしを「うたうたい」として見てくれた一番最初の人
だったかも知れない。
当日までに、オリジナル曲は8曲生まれて、Yちゃんが作ってくれた
衣装を着て唄った。
ライブには友達やお店のお客さんやお店で出会えた人たちが
歌を聴きに来てくれた。
ライブが終わってから、おつかれさまといってYちゃんから渡されたお金。
はじめてもらう自分の歌が生み出したお金は、それまでの人生で
手にしたことがあるどんなお金とも違う重みのある特別なお金だった。
ライブの後、一枚のハガキがお店に届いたのだと聞いた。
それはお店宛てに届いたハガキだったのだけれど、
”自分の心の底を覗き見るような時間でした。
これからも、胡池さんにはずっとうたい続けて欲しい”
と書かれていた。
そのハガキが偶然にも、その頃玄関に飾っていたタテタカコさんの
「狼の皮を被った羊」という大好きなポストカードと同じだったことも、
わたしの歌を聴いてそんな風に感じてくれたことも、それを伝えて
くれたことも、全部が全部本当に驚きと嬉しさでいっぱいだった。
歌を唄うことは、ときにものすごく孤独で、先の見えないいばら道
だけれど、わたしはその道をずっと一人で歩いてきたわけじゃなくて、
いつだって誰かが道しるべをしてくれていた。
山を登っていてどきどき見かける、人の手によって積み上げられた
石の道標ケルンみたいに、道しるべになってくれたたくさんの人たち。
苦しいときには、同じ時間を過ごしたそのケルンみたいなみんなの顔や
みんなからもらったものをまた感じてみる。
今は、Yちゃんは二人のお母さんになって、もうお店もない。
きっと素敵なお母さんになっていると思う。
そして、わたしはまだ歌を唄い続けてる。
もう二度と戻ることはできない場所だけれど、それはわたしの中にずっと
消えずにあり続けるものだから、わたしはいつだってそこに帰ることができる。
そんな場所が、歌を唄い始めたあの日から、心の中にひとつずつ増えている。